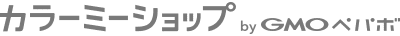作り手を訪ねて #1
ひもの屋しあわせうお
〜熊野の海と人が育む干物
熊野の海の恵みを丸ごと閉じ込めた干物を、夫婦で丁寧に作り続ける「しあわせうお」。
受け継がれた伝統の味を、あなたの食卓へ届けます。
世界遺産・七里御浜が目前に広がる三重県熊野市木本町で、伝統の味を夫婦で守りながら干物を作っている「ひもの屋 しあわせうお」。
熊野で水揚げされた新鮮な魚の丸干し、定番のアジやサンマの開き、みりん干しなど年間を通して約20種類の干物を作っています。
店を切り盛りする石本法夫さんにお話をうかがいました。

|市場で働き、もとの自分に|
家電量販店や派遣会社で働いていた石本さんが、熊野漁業協同組合(熊野市)の職員となったのは2011年。
「それまでは仕事で大変なことが多くて、心が疲れていた。そんな時に知ったのが漁協の仕事。はじめは公務員のようなイメージだった」
はじめは魚の種類も見わけられませんでしたが、裏表のない市場の人たちと仕事をするうちに「もとの自分に戻っていった」といいます。
2年目で大先輩から任され、札を読ませてもらえるように。
数字を読みまちがえると怒号が飛びましたが、「市場での仕事を通して、幅広く人を見られるようになった」そうです。

▲一枚ずつ丁寧に並べる石本さん
|老舗から受け継いで|
市場で働いて8年が過ぎた頃、いつも魚を仕入れに来ていた地元で40年続く干物屋「浜口商店」が店を閉めたと聞きました。
「あの味がなくなるなんて」。
その日のうちに店主の浜口一衛さんに会いに行きました。
「気にいったやつになら場所だけやなく、作り方も教えるけどな」
「ぼくやったら、どう?」
「おまえやったら全部みたらなあかんなぁ」
そう交わした言葉を、今でもよく覚えています。
「全部みたらなあかん」とは熊野の言葉で、「すべて面倒を見てあげないといけない」という意味です。
作る人の幸せ、お客さまの幸せ、生産者の幸せ。
関わった人みんなを幸せにしたいという思いを込めて、店の名前は「しあわせうお」に。
コロナ禍に入る前の2019年夏にオープンしました。

▲早朝からの作業は手際良く進んでいく
熊野の海と人が育む、昔ながらの干物の味を。
旅の思い出に、日々の食卓に。
|夫婦二人で切り盛り|
地元で愛されてきた「浜口商店」の味を守っていけるよう、浜口さんから干物作りのいろはを教わりました。
石本さんが「かあちゃん」と呼ぶ妻の佳織さんは当初、店に関わる予定はありませんでした。
佳織さんは別の仕事をしていましたが、忙しくて手がまわらず応援に来てもらううちに、なくてはならない存在に。
魚をさばく腕前は抜群で、「ぼくもさばきますが、手先の器用さがちがう。かあちゃんがおらんと回らない」と笑います。

▲佳織さんの魚さばきは見とれるほどの手際の良さ
|熊野の魚は脂抜けがいい|
石本さんが働いていた遊木漁港(熊野市遊木町)では主に丸干しに加工する魚を仕入れています。
「熊野は脂が抜けた魚が水揚げされる。種類も多い。だから、乾かす(干物)のに適しているんでしょうね」
熊野の冬の風物詩と言えば、ずらりとつるされたサンマの丸干し。
晩秋から冬にかけて三陸沖から熊野灘まで南下してくるサンマは脂が落ちて身が引き締まり、加工に向くことから、熊野では古くから丸干しやさんまずし(サンマの姿ずし)、なれずし(サンマとご飯を発酵させたすし)が作られてきました。
丸干しは塩漬けにしたサンマを内臓もそのまま乾燥させたもので、中でもかなり脂が抜けて、干し上げられたものは地元で「かんぴんたん」と呼ばれます。
しかし、地球温暖化の影響で数年前からまとまって水揚げされなくなりました。
地元では脂ののりが似た他産地のサンマを仕入れ、丸干し文化を残そうと力を尽くしています。
「しあわせうお」でも晩秋から春ごろまで製造し、熊野の味を全国のファンに届けています。

▲仕込みが終わった「さんまのひらき」
|干物を選んでくれるから|
海の恵みに感謝しながら、たくされた味を守り続ける石本さん。
「たくさんの種類の食べ物がある中で、たまたま干物を食べたいと思う人がいてくれるから、ぼくらは作ってる。毎日食べてほしいとは言わない。思い出してもらえたらうれしい」
魚ばなれが進んでいると聞くこともありますが、「干物は庶民の味で、誰でも食べられるもの。食べたい人みんなが腹一杯、食べてほしい」とほほえみます。
干物作りをはじめた頃の気持ちを忘れず、日々、海の恵みに向き合っています。
(2025年6月取材)

「しあわせうお」の干物は熊野で水揚げされた新鮮な魚を丸干し、開き、みりん干しなどに仕上げています。
地元で受け継がれた味を大切に、脂抜けの良い魚を丁寧に加工。
季節によって種類も変わり、年間約20種類を製造しています。